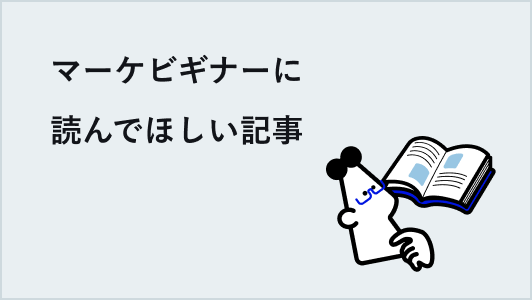ECモールの運営には欠かせない指標であるGMV(Gross Merchandise Value:流通総額)ですが、詳しい意味や算出方法などは実はよく分からないという方は多いのではないでしょうか。
しかし、GMVは活用することで売上とは違った側面から企業の成長を測れたり、売上自体の向上に効果的なアプローチができたりと便利な指標でもあります。
そこでこの記事では、
・GMVの意味
・GMVの計算方法
・GMVの企業事例やランキング
などをご紹介しています。
目次
GMVとは
GMVとは、Gross Merchandise Valueの略称で、日本語に訳すと「流通総額」のことです。つまり、モール型ECサイトやアプリなどのプラットフォームにおいて顧客が購入した商品の総額のことを指します。
GMS(Gross Merchandise Sales)とも呼ばれることがありますが、意味合いはほとんど同じです。
GTVとは
一方、よく似た言葉にGTVがあります。これは、Gross Transaction Valueの略で、日本語では「総取引額」と訳せます。
GMVとGTVを区別する
GMVとGTVの違いはどこにあるのでしょうか。
まずは、それぞれの用語を分解して詳しい意味を確認してみましょう。
- GMV
「G」Gross:(税込みで)総額の、全体の
「M」Merchandise:商品
「V」Value :価値、値
- GTV
「G」Gross:(税込みで)総額の、全体の
「T」Transaution:業務
「V」Value:価値、値
どちらも同じような言葉ですが、GTVのほうがより企業の業務の一環としての意味合いが強いことが分かります。
実際、日本ではほとんどの場面で「GMV」を用いますが、一部株式や有価証券報告書に関する取引の場面ではGTVが使われることもあるようです。
GMVとの関連性が深い「マーケットプレイス」の定義

モール型ECサイトとは、1つのECサイト内に多くのショップやその商品が混在している状態のものを指します。
モール型ECサイトは数多く存在しますが、それらは
1.マーケットプレイス型
2.テナント型
の2種類に分類されます。
このうちGMVと関連性が深いのがマーケットプレイス型と言われています。ここでは2つの型の定義を比較することで、マーケットプレイス型の特徴を把握しましょう。
1.マーケットプレイス型
マーケットプレイス型とは、ECモールに各企業が商品を出品する形態のことを言います。
マーケットプレイス型の代表格でもある、Amazonのサイトを思い浮かべると分かりやすいでしょう。
実店舗で例えるならば、スーパーにある地場商品のコーナーのように、1つのスペースに各生産者が出品した野菜や加工品が並べられている状態によく似ています。
マーケットプレイス型のメリットは、商品を出品するだけでビジネスが開始できる手軽さにあります。商品データ管理やサイト運営はすべてECモールが行うので、細かな作業が軽減されるのです。
一方、サイト自体のデザインやコンテンツに特色が出しにくく、商品の独自性やブランドイメージが打ち出しにくいというデメリットもあります。
2.テナント型
テナント型とは、ECモール内に各企業が出店している形態のことです。代表例を挙げるとすれば、楽天市場やYahoo!ショッピングなどがそれに当たります。
テナント型を実店舗に例えるならば、ショッピングモールのようなイメージと言えます。大きな店舗の中に、各ショップが軒を連ね、「テナント料」を支払ってビジネスを行います。
マーケットプレイス型とは違い、テナント型では運営や事務的な業務は全てショップ側の仕事となります。
しかし、ショップごとのデザインやコンテンツはある程度の自由が利くので、独自性やブランドイメージが顧客に伝わりやすいというメリットもあります。
GMVという言葉が広まった背景
GMVという言葉が一般に広まったのは、メルカリの登場がきっかけと言われています。
メルカリとは、インターネットフリマ(フリーマーケット)アプリの一種です。自分の家にある不要なものや他人の不要なものを、アプリやWebサイトを通じて売ったり買ったりでき、ネットニュースなどにもたびたび取り上げられる人気のサービスです。
購入ページに入ると個人が出品した商品がずらりと並んでおり、マーケットプレイス型のECモールであることが分かります。
メルカリのサイト内にも、「GMVが伸び続ける仕組みを作ること」がミッションであると明記されています。
このように、マーケットプレイス型のECモールでは、GMVがいかに伸長するかが企業成長の指標とされることが増えているのです。
GMVがなぜ重要なKPIとされているのか
なぜマーケットプレイス型のECモールでは、GMVがKPI(Key Performance Indicator:主要業績評価指標)として使われるのでしょうか。
それは、GMVが売上に直結する指標だからです。つまり、GMVを上げると売上も伸びるのです。
GMVを向上させる要因としては、「利用者数の増加」と「顧客の購入金額の増加」が挙げられます。
このうち、モール側ができる施策は主に「利用者の増加」を狙ったものです。
“会員費無料”や”3か月間手数料無料”などといったキャンペーンを見たことがある方も多いのではないでしょうか。
このように多くのマーケットプレイス型ECモールでは、利用者の増加からGMVを向上させ、結果売上アップにも結びつけようとしているのです。
関連記事:ECサイト分析の手順とKPIを紹介!改善方針やツールも解説
GMVの計算方法

では実際にGMVを算出するとき、どのような計算式を使うのでしょうか。
GMVの計算式は次の通りです。
GMV=総購入者数×顧客単価×リピート回数
顧客単価とは、顧客一人当たりが1回の買い物で支払った金額の平均のことです。
また、計算式に使ったそれぞれの指標は、次のように因数分解できます。
総購入者数=総訪問者数×購入率
顧客単価=平均買い回り点数×平均商品単価
リピート回数=総取引回数÷総購入者数
このように、それぞれの指標を細かく分けていくことで、GMVがECモールでのKPIにどのように関わっているかが分かります。
こうした関係性を把握しておくと、GMV向上の施策を考案するときの現状把握がより正確に行えるのです。
関連記事:リピート率を上げるためのアイデア/リピート率の基準や計算方法まで徹底解説
テイクレートとは
テイクレートとは、企業の取り分という意味です。マーケットプレイス型のECモールでは、商品の売上ではなく、決済時の手数料を収益源としています。
そのため、企業の売り上げを計測したいときには、
売り上げ=GMV×テイクレート
の算出式を使います。
たとえば、1,000円の商品が売れてそのテイクレートが10%だった場合、企業の取り分は1000×0.1=100(円) ということになります。
ちなみにテイクレートはサイトによってさまざまですが、割合が高いほどサイトのブランディングが成功していると言えます。それは、ショップがサイトに出品することにどれだけの価値を感じているかを測ることができるからです。
国内ECモールのGMVランキングTOP5

ここからは、国内ECモールのGMVランキングTOP5をご紹介します。
企業情報と合わせて、実際の総流通額も掲載しているので、ECモールの市場規模感も合わせて確認してみてください。
ランクイン企業は以下の5社です。
・楽天
・Amazonジャパン
・Yahoo!ショッピング
・ZOZOTOWN
・au Payマーケット
第1位:楽天(約5.6兆円)
日本の大手通販企業である楽天の総流通額は5兆円を突破しています。これは、2023年2月に楽天グループから発表された速報値によるものです。
コロナ禍におけるネットショッピング需要の高まりを背景に増加した顧客の定着が進み、
総流通額5兆円とされていた前年度から更に増加しています。
尚、この数値は楽天市場、トラベル、ブックス、ゴルフなどの各サービスの流通額を合算したものです。
参考URL:https://corp.rakuten.co.jp/news/press/2023/0214_06.html
第2位:Amazonジャパン(約3兆円/推定)
世界的通販企業・Amazonの日本法人であるAmazonジャパンの流通総額は、約3兆円です。
Amazonジャパンは正式には総流通額を発表していないため、ここでの数値は、米Amazonが公表した「年次報告書」などの数値をもとに推定しています。(1ドル=131円換算)
参考URL:https://www.fashionsnap.com/article/2023-02-15/us-amazon/
第3位:Yahoo!ショッピング(約1.6兆円/推定)
国内で大手通販サイトといえば、楽天、Amazonジャパンと並んで出てくることの多いYahoo!ショッピングが第3位です。推定総流通額は約1.6兆円です。
これは2023年3月期決算におけるYahoo!ショッピングとグループのZOZO、アスクル運営の通販サイト「LOHACO(ロハコ)」とアスクル子会社のチャームを合計した金額となっています。
参考URL:https://nethanbai.co.jp/archives/14733
第4位:ZOZOTOWN(約5,000億円/推定)
第4位は、Yahoo!ショッピングと同じくZホールディングスに属するZOZOTOWNです。
これは22年3月期決算の情報を元にした流通総額です。前期比21.3%増となっており、ECマーケットの中でもファッションに特化していることが強みになっています。
参考URL:https://www.wwdjapan.com/articles/1357001
第5位:au Payマーケット(約2,500億円/推定)
第5位のau PAY マーケットは、KDDIが主にauユーザーをターゲットに展開しているECモールです。以前はau Wowma!の名称で親しまれていたため、こちらの名前で認識している方も多いかもしれません。
au APYマーケットは流通総額を公表していません。しかしインタビュー記事にて増益を重ねていることは公表しており、上記はKDDI連結の総売上をもとに算出・推定した金額になります。
参考URL:https://www.tsuhanshimbun.com/products/article_detail.php?product_id=6088
GMVにおいて注目したいEC企業7選
では、最後にGMVにおいて注目したいEC企業を7社ご紹介します。
どれも一度は聞いたことのある有名なものですが、各社ともGMVを向上させる取り組みや、GMVの活用で業績を伸ばしています。
ご紹介するのは以下の7社です。
・メルカリ
・Amazon
・PayPay
・楽天
・Yahoo!
・ZOZOTOWN
・au Payマーケット
それではひとつずつ見ていきましょう。
メルカリ

メルカリでは、2023年度6月期連結決算(2022年7月~23年6月)にて、GMVが9,846億円と
「1兆円規模に成長した」ことを発表しました。
さらに、今後の事業方針として本業とのシナジーを狙ったFintech系サービスにも引き続き投資を積極的に行うことを考えているようです。
これらの目的はユーザー体験の向上です。顧客はメルカリのサービスを利用することで、購入体験のスムーズさをより感じることができます。
すると、「次も利用してみよう」と考えるようになり、次第にリピーターを獲得できるのです。
リピーターの増加は買い回り点数や商品単価向上にも有効です。
このように、顧客満足度を上げることで買い回り点数や顧客単価を改善し、GMV向上を目指すこともできるのです。
参考URL:https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2308/10/news175.html
Amazon
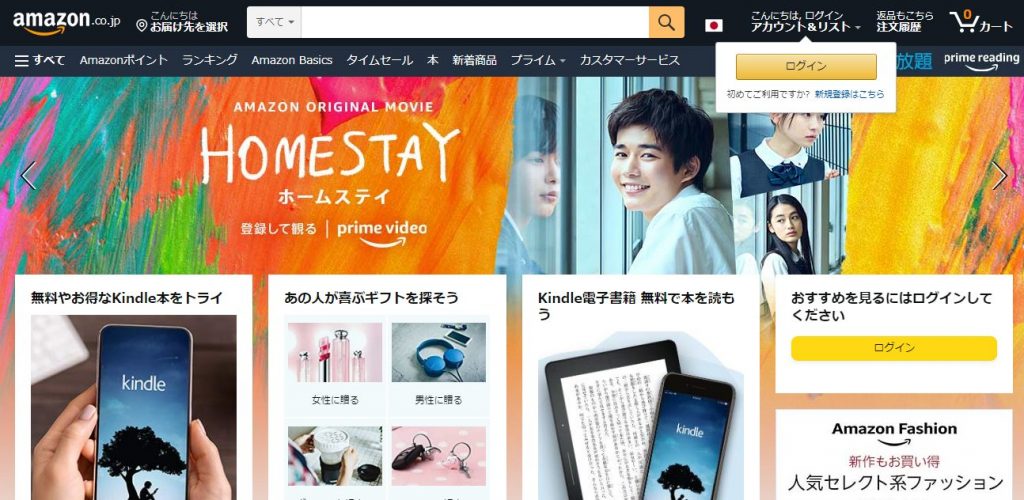
画像引用:https://www.amazon.co.jp/
2023年2月に発表した2022年度決算で、Amazonは年間GMVが5,139億ドルだったと発表しました。
一方、米大手小売業のウォルマートが同年1月に発表した年間売上高は6,113億ドル。ウォールマートではほとんどの商品を直接販売しているため、GMVはほぼ売上高と等しいと考えられています。
Amazonが発表した売上高を見ると、5,139億ドルとされており、一見企業規模はウォルマートほどではないように見えます。しかし、ここでの売上高とはあくまでAmazon自体の売上高であり、出品業者の販売額は含まれていません。
GMVの測定を行うことで、企業の隠れた市場への影響力を知ることが可能になるのです。
参考URL:https://netshop.impress.co.jp/node/10620
PayPay

PayPayは、ソフトバンク株式会社とヤフージャパンが設立したオンライン決済サービスです。ECモールとは異なる業態ですが、顧客数と利用回数を増やして売上を伸ばしていく利益構造は共通しています。
PayPayでは株式公開を目指すことなどから、GMVの公表に踏み切っています。それによると、2022年度のGMVは5.4兆円で、前年度比の67%増にも上りました。
こうした急成長を支えたと考えられるのが、顧客数の増加です。2023年2月時点で5,500万人を超えたユーザー数に後押しされ、2022年度の決済回数は47億回を突破し、さらに伸長の兆しを見せているようです。
利用者数の増加が、GMV向上に影響している分かりやすい例であると言えます。
参考URL:https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1323877.html
参考URL:https://about.paypay.ne.jp/pr/20230710/01/
関連記事:ネット決済とは?導入メリットや種類、比較ポイントなどを解説
楽天

画像引用:https://www.rakuten.co.jp/
楽天は前述の通り、日本一のGMVを誇る企業です。2022年度には年間約5.6兆円を超える規模の取引がオンラインで行われていたことも分かっています。
楽天のGMVを大きく伸長させた要因の一つに、同一ブランドで商圏を作ってしまい、その中での取引を活発化させたことにあります。
楽天では、主力の楽天市場だけでなく、楽天トラベル、楽天証券、楽天でんき、楽天モバイルなどさまざまなサービスを提供しています。
そして共通のカードやポイントを使いまわせるようにすることで、楽天商圏内での回遊率を高めたのです。
このような工夫により、顧客数や買い上げ点数の増加、購入回数の改善などが可能になります。その結果、楽天は現在のポジションまで昇りつめたのです。
参考URL:https://corp.rakuten.co.jp/investors/financial/indicators.html
Yahoo!

ヤフーの持ち株会社であるZホールディングスによると、2022年度のGMVは前期比7.4%増の4兆1,143億円でした。
オンライン決済サービスの「PayPay」を活用したキャンペーンはグループ内のEC関連サービスの利用拡大にもつながっています。
ヤフーにおいても楽天と同じように、顧客を囲い込みその中を生活圏にしてしまうことでGMV向上を図っています。
こうした手法は中長期的な利益基盤の構築も同時に行えるため、今後更なるGMVの伸長が期待できるのです。
参考URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/8d4921216da9c07bfbb009712fe8822dc3ff757e
ZOZOTOWN

画像引用:https://zozo.jp/
ZOZOTOWNは、2022年度のGMVが前期比の21.3%増の5,088億円であったと発表しました。
実は、ZOZOTOWNでは、新規顧客の増加に伴い平均商品単価は減少を続けています。
それでもこれだけのGMVの成長率を見せるのは、セット買いや親会社であるZホールディングスと組んでいる「ペイペイモール」との併用買いの多さが影響しているからとされています。
このように、GMVを因数分解してさまざまなアプローチを行うことで、問題点を補い数値の向上を目指すことが可能になるのです。
参考URL:https://www.wwdjapan.com/articles/1357001
au PAYマーケット

画像引用:https://wowma.jp/
au Payマーケットでは、リピート利用の顧客増加が目立っています。
このリピート客の多くは、au利用者へ向けた会員優遇プログラムである「au スマートパスプレミアム」の会員であると言われています。
このプログラムでは、月額料を支払うことでさまざまなエンタメコンテンツの利用が可能なほか、au Payマーケットでも送料無料などお得に買い物ができるのです。
auスマートパスの会員は、そもそも一般顧客よりもauに対するロイヤリティが高い層です。この層に積極的に働きかけることで、購入回数や顧客単価アップの観点から効率よくGMVの向上を実現していると言えます。
参考URL:https://netkeizai.com/articles/detail/5218
関連記事:顧客ロイヤリティとは?メリット・調査法・向上の施策事例を解説
まとめ
GMVは、モール型ECサイトやアプリなどのプラットフォームにおいて、顧客が購入した商品の総額のことです。
GMVを向上させることはサイト自体の売上アップに繋がるだけでなく、計測することで表面上は見えない市場への影響力なども分かります。
GMVの概念と活用方法を正しく理解し、ECサイトの運営に役立ててください。